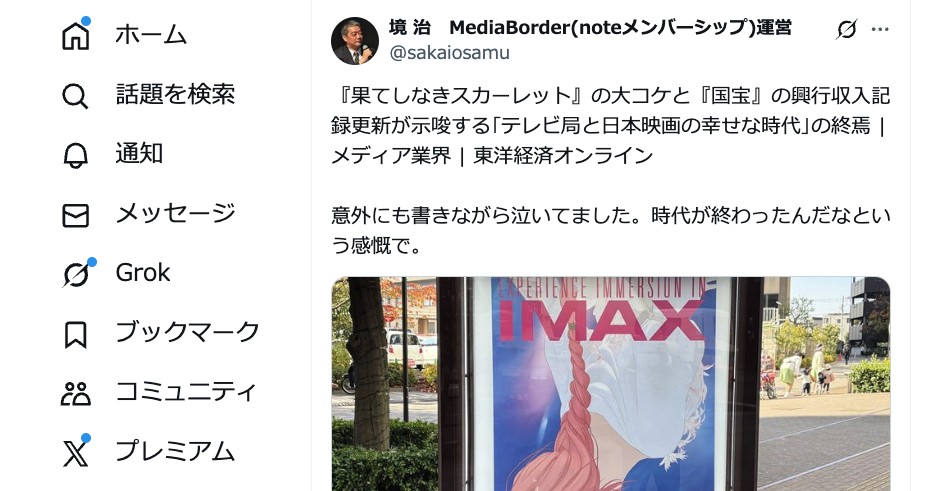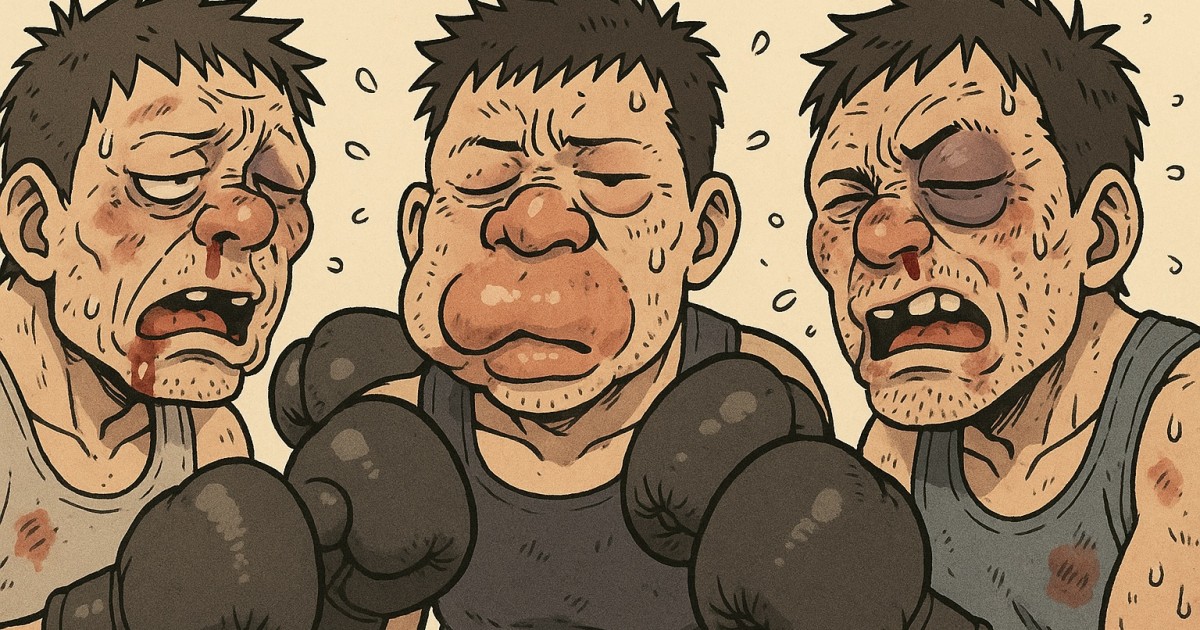危機感なさすぎのメディア界に数多くの事例を突きつける〜下山進氏の「持続可能なメディア」

連載記事「2050年のメディア」を書籍化
下山進氏と言えば「2050年のメディア」だ。これは2019年に出版された書籍の名前だが、その後も同氏が連載している記事のタイトルでもある。
書籍のほうは正直、釣りタイトルだなあと感じた。書かれているのは未来のメディアではなく2000年代の読売新聞とYahoo!に日経も絡めたメディア間の覇権争いが主だった。タイトルと中身が違うじゃないかとぶつぶつ言いつつ面白く読んだ。
ただどうやら、「2050年のメディア」という言葉は下山氏のスローガンのようなもので、同氏がメディアについて書いた文章の総称として使っているのだろう。
その後、連載のほうも見かけたら必ず読んでいる。見かけたらという言い方になるのは、どこに載っているのかよくわからないからだ。今回の本の「はじめに」でようやくわかったのだが、掲載誌が「サンデー毎日」「週刊朝日」「AERA」と移っていたのでどこで読めるか、印象が交じり合っていたのだ。もっと言うと、それぞれの紙のメディアで読むわけでなく、Yahoo!やスマートニュースなどで読んでいた。だから「見かけた」の言い方になったのだ。ここにも、今のメディアの難しさが見えてくるが、それはまた後述する。
とにかく、そんな漂流してきた連載をもとにした書籍が「持続可能なメディア」だ。前置きがややこしいかな。
本題に入る前に、ちょっとした愚痴を書いておく。最初、この本は読みにくかった。「コラムをもとにしてつくられています」と「はじめに」に書かれているように、連載時の文章をテーマに沿って並べて、その間を埋めるように書籍化に当たって文章が書き加えられている。だから「つくられて」いるとあったわけだ。
その構成が、慣れるまでとても読みにくかった。数年前のコラムが、その触れ込みなしに始まっているのでついつい、現在のこととして受け止めてしまう。時に、あれ?今は少し違うんじゃない?と思っていると掲載時の日付が出てきて、ああ3年前のこと書いてるんだなとわかる。いつのことを書いているのか、そのパートに入る前に何らか示してくれたらわかりやすかったのにと思った。
メディアが持続するために何が必要かのメッセージが貫かれている
「はじめに」の冒頭に、書籍「2050年のメディア」について「しょせんはカネの話ではないか」と新聞記者に批判されたとある。そこに現在の大手メディアの危機が、特に新聞などジャーナリズムのメディアの危機が凝縮されていると思った。失礼な発言だが、お気楽で無責任でもある。どう見てもベテランの人物だろうが、もはや50代でも逃げ切れない状況なのに、その程度の危機感の薄さなのだ。
危機感が薄いのがメディアの最大の危機だ。フジテレビの問題を他人事としか見ていないのだろう。そういう人は救いがないので、そういう人を見てヤバいと感じる人こそ読むといいと思う。
さてこの本は、非常に明確なメッセージで貫かれている。持続可能、つまりこれから生き残るためには2つのポイントが必要だというのが下山氏の主張だ。
その2つとは「そこでしか読めないものが載っていること」「それをデジタルで有料で届けること」。そしてこの本では、主に1つ目のポイントについて様々なメディアに取材している。独自のコンテンツを作るためにどんな考えで何をしているかを、徹底的に追求している。
そして一貫して「前うち」を批判する。「前うち」とは、正式な発表の前に取材相手からリークなどで特別に情報を得て報道することだ。そんなことしても「持続可能」にならないと、何度も何度も主張している。
「抜いた抜かれた」が記者の世界の真骨頂らしいが、私も前々からそれが不思議だった。前にある記者に聞いたのだが、ある人物の逮捕がいつかを知るために、検察のキーマンが山歩き好きなので一緒にひいこら山に登ってようやくその日の昼に逮捕だと午前9時に聞き出し、仲間に連絡して「今日、逮捕へ」とスクープを出したと言う。
そんな話を面白げに語る記者の話に私は白けた。12時にわかることを9時に出せたから、なんだと言うのだろう。だが記者たちは、読者視聴者からするとムダなことを争い、「前うち」できると鼻高々で上司からも褒められ、ライバル記者を悔しがらせた。何になるの、それが?読者視聴者が評価しないことを仲間内で競い合っている。馬鹿みたいだ。いや馬鹿なのかな?
もともとそう思っている私には、下山氏のレポートは痛快だ。「前うち」ニュースの価値は出た瞬間に消えてしまう。それより、独自の視点で書かれたそのメディアにしか載ってない情報や考察のほうが長い期間、価値を持つ。それが「持続可能」なメディアに繋がるのだ。
金沢文化の記事が一面に載る北國新聞、買収とMBOでよみがえったハルメク
この本は多岐に渡る事例取材をもとに構成されている。「2050年のメディア」のようにストーリー性は必ずしもないので、「拾い読み」しやすい。私もしばらく持ち歩いて、待ち時間などに目次から読みたいパートを選んで少しずつ読んだ。
取り上げた事例の中でもっとも驚いたのが、北國新聞だった。石川県をエリアとするこの新聞は時に、金沢の伝統文化の記事が一面に配置される。県民が読みたい記事を優先するし、金沢文化の掘り下げには力を入れているのだ。そのせいか、新聞全体が20年で半分くらいに部数を落としているのに、北國新聞は9%しか落ちていないという。
北國新聞は新聞業界では「自民党べったり」だと批判されるそうだ。だから連載で取り上げた回は下山氏に「北國新聞はないよ」と批判を言ってくる人もいた。だがそんな人たちは肝心の北國新聞の中身を読んでいない。中身を知らずに批判するのはジャーナリズムとしてどうなのかと思うが、新聞記者にありがちだなあとこれも偏見を込めて言いたい。
その北國新聞が2024年1月の能登半島地震をどう報じたかはこの本最大の読みどころだと思う。これはぜひ書籍を手にして読んでほしい。
雑誌「ハルメク」のパートはまったく別の意味で面白い。高齢者向け雑誌として大成功したことはなんとなく知っていたが、一度大きく傾き、買収で新しい経営になって持ち直し、MBOによって新たな成長軌道に乗ったことがレポートされる。メディア企業は営利企業であり、だからこそ経営手腕が重要で、雑誌の中身にも影響する。そして特定の読者を掴めば雑誌と物販が両輪になれることも理解できる。
メディア企業は経営者がダメだと会社として危うくなることはフジテレビ問題ではっきりわかったと思う。ではどんな経営がメディア企業に必要なのか、「ハルメク」の事例が教えてくれる。
事例でもう一つ、米子市を中心としたケーブルテレビ局、中海テレビが非常に詳しくレポートされているのは嬉しい。私も2018年に訪問し、何から何まで驚きだったことを思い出す。当時の記事をほじくり出してMediaBorderでも後日掲載したい。地域メディアに携わる人なら、知っておきたい事例だ。
ともかく「持続可能なメディア」はユニークで参考になる事例であふれている。メディア企業の関係者、研究者は必携の書籍だ。
「2050年のメディア」を購読することができないもどかしさ
「持続可能なメディア」には一つ不満がある。それは「そこでしか読めないもの」については国内外様々なメディアを取材しよく理解できるが、「デジタルで有料で届ける」ことについては言及が少ないことだ。そしていま、本当に難しいのがここではないかと思う。というのは、下山氏の連載「2050年のメディア」でさえ、「購読」が難しいからだ。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績