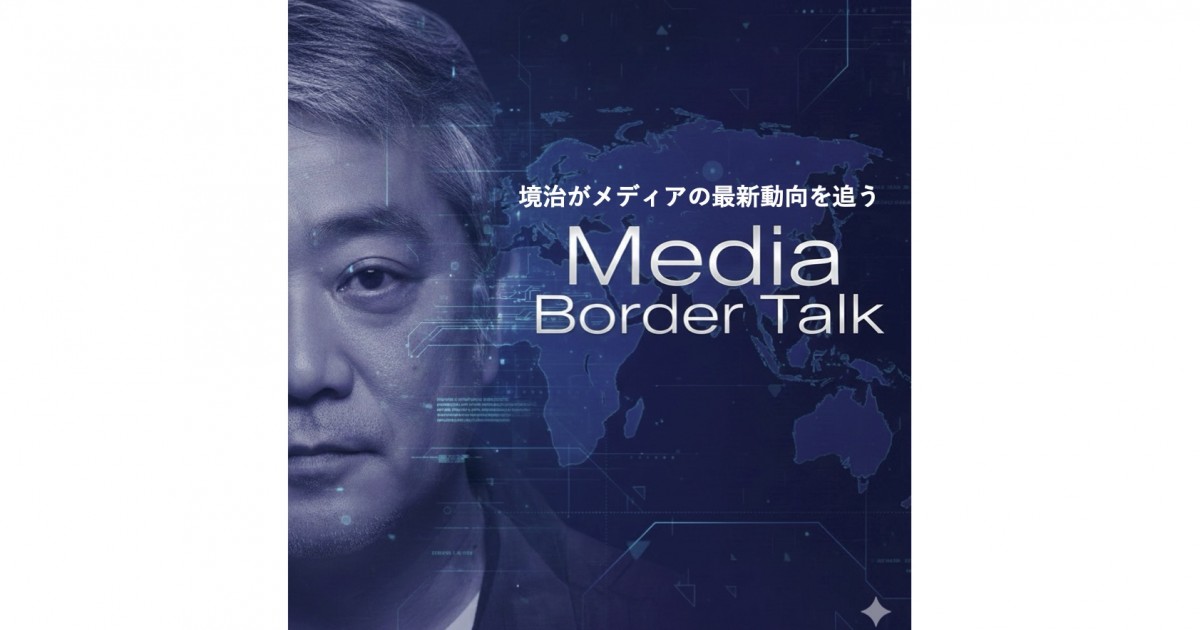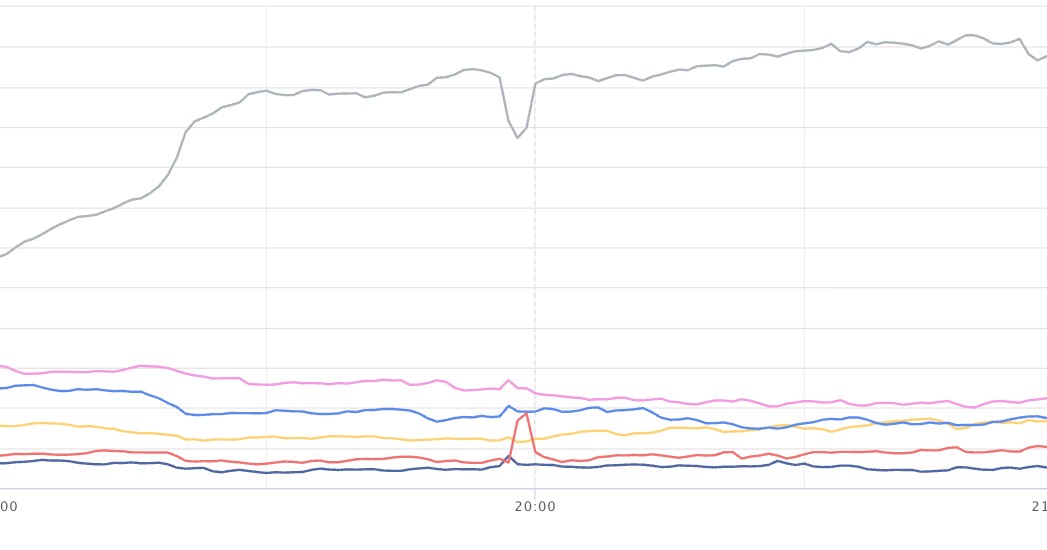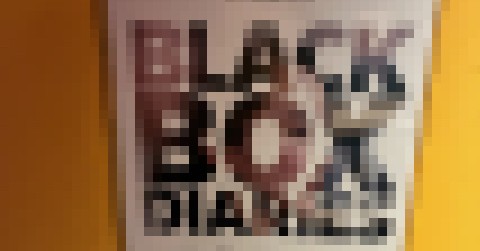映画「国宝」興収100億突破は、日本のコンテンツビジネスの主役交代の象徴だ

6月に筆者が干渉した時のスクリーン入口のポスター
フジテレビ映画だらけの実写興収ランキングに躍り出た『国宝』
映画「国宝」が累計興行収入105億円を記録した。100億円の大台に実写の日本映画が到達したのは22年ぶりだと話題になっている。
7月下旬に70億円に達した時、ひょっとして100億円を狙えるのではと囁かれ始めていた。だが筆者は懐疑的だった。すでに7月18日に『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が公開され4日間で73億円という凄まじい成績を叩き出していた。映画館は『鬼滅』のためにスクリーンを使い切る勢いで、『国宝』は1日3回程度の上映になっていた。さすがにこれから30億円を稼ぐのは無理がある。タイミングが悪かった。そう読んでいたからだ。
だが夏休みの映画館が『鬼滅』で活況を呈する中、予約サイトでふと『国宝』のスクリーンに目をやると毎日売切れが続出していた。上映回数が絞られることでかえって盛り上がっていたようだ。1ヶ月ほどで30億円を稼ぎ、筆者の想像を超えて100億越えを果たした。
ここで、過去の実写日本映画の興行収入ランキングを並べてみよう。
-
1位 『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』 173.5億円 (2003年)
-
2位 『南極物語』 110億円 (1983年)
-
3位 『国宝』 105.4億円 (2025年)
-
4位 『踊る大捜査線 THE MOVIE』 101億円 (1998年)
-
5位 『子猫物語』 98億円 (1986年)
並べてみて気づくことがある。『国宝』以外はフジテレビ映画なのだ。『踊る大捜査線』2作はもちろん、ドラマの映画化。『南極物語』と『子猫物語』は80年代の単独の映画作品だがフジテレビ制作。奇しくもこの2作には製作者として日枝久氏の名がクレジットされている。
すると、『国宝』100億越えの象徴的な意味が見えてくる。それは、日本のコンテンツビジネスの中心がテレビ局ではなくなったことだ。フジテレビ問題が露呈した2025年に『国宝』が公開されたのは、時代的必然だったのかもしれない。
『国宝』がヒットしたのは、クオリティのためにお金と時間をかけたから
『国宝』の製作幹事はミリアゴンスタジオというあまり聞いたことのない会社だ。ソニー・ミュージック・エンターテイメントの子会社アニプレックスが2023年にオリガミクスパートナーズを子会社化して名称変更して生まれた新しい会社だった。アニプレックスはご存知の通り『鬼滅』をアニメ化した会社だ。
だから今の映画館は、方や『鬼滅』の新作がスクリーンを埋め尽くす一方で、6月からのロングランで『国宝』が100億越えを達成する、アニプレックス祭りとなっている。
ミリアゴンで『国宝』をプロデュースしたのが村田千恵子氏で、Cocotameというサイトにインタビュー記事が2回に分けて掲載されている。
これを読むと、村田氏が李相日監督との縁で『国宝』をプロデュースすることになったのと、ミリアゴン設立に村田氏が関わった、いい流れがこの作品を生んだことがわかる。だから偶発的なヒットではあるのだが、ミリアゴンの、そしてアニプレックスの、つまりはソニー・グループのコンテンツビジネスに向き合う姿勢がもたらしたヒットだとも言える。
『国宝』はなぜヒットしたのか。いろんな理由があるが、根源的には「お金と時間をかけたから」だと私は思う。立ち上げから5年かけており、脚本作りだけで2年もかけたという。撮影に入る前の準備も入念だ。中でも、主演の吉沢亮が歌舞伎の稽古に一年半を費やしたことは驚きだ。
映画にお金がかかるという時、普通はセットやVFXのコストの話だ。だがそれ以上に『国宝』は、映画のクオリティを総合的に高めるためにお金を使い、時間もかけている。『国宝』がなぜヒットしたか。クオリティのためにお金と時間をかけたから。そこに集約できると思う。
『国宝』が公開されてから1ヶ月ほど、私のFacebookのタイムラインではあのポスターのビジュアルが連日並んだ。周囲の大人たちがあまりの映画の素晴らしさに震えたからだ。私も遅れて見に行き、震えた。吉沢亮も横浜流星も、少年時代から歌舞伎に打ち込んできた青年にしか見えない。そんなに本気で作られた日本映画は滅多にない。関わる誰もがこの作品に自分ができるものを注ぎ込んだ、その結実が見た者を震わせ、それが拡散されてこのヒットに繋がった。精神的なことを書いているようで、それができたのは「お金と時間」をかけたからだと理解してもらいたい。
テレビ局が、日本のコンテンツビジネスの王座から転がり落ちた
少なくとも2000年代までは、日本のコンテンツビジネスの中心はテレビ局だった。映画界を90年代のどん底からテレビ局が救ったことは何度か書いた。その象徴が『踊る大捜査線』であり、テレビドラマを映画化するとヒットするという、今は当たり前の公式を作ったのも『踊る』でありフジテレビだった。
『踊る』以前から、映画界はテレビ局に牛耳られていた。私は90年代に映画会社の宣伝部とポスター制作の仕事をしたが、テレビ局のプロデューサーの前で名だたる映画会社の人々が小さくなっているのを見てきた。テレビ局が関わらないと映画はヒットしなかったからだ。
2010年代になると様相が変わり、テレビ局が関わらない映画がヒットするようになった。『シン・ゴジラ』『君の名は。』が典型で、他にも、特にアニメではテレビ局が蚊帳の外の映画がヒットしていた。一方、日本も韓国のようにコンテンツを海外展開すべきとの論が言われるようになった。その際には、最重要プレイヤーとしてテレビ局が期待される。一部の政治家は、TVerを海外でも見られるようにすれば、日本コンテンツの出口になると意見している。
だが私は無理だと思っていた。『国宝』のヒットでそこがはっきりしたのではないか。斜陽産業のテレビ局が頑張らなくても、ソニー・グループがお金と時間をかけたコンテンツを海外に展開するだろう。他にも、別のプレイヤーはいる。テレビ局には無理です、海外展開は。
その理由をもう少し詳しく書こう。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績