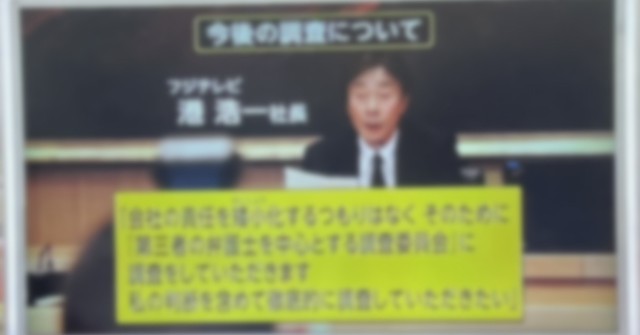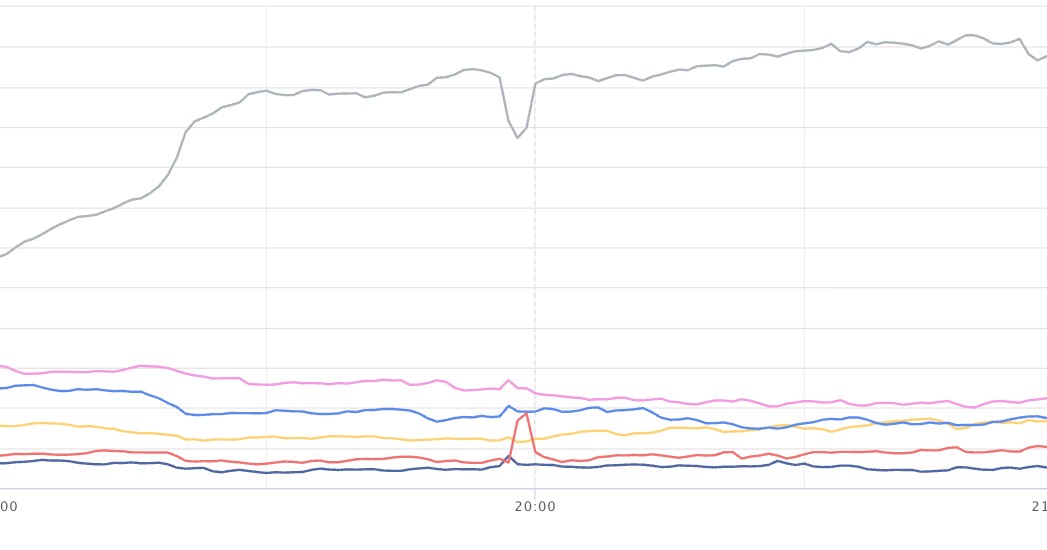「踊る大捜査線」が映画館をテレビにした革命〜スピンオフ「容疑者 室井慎次」もメガヒット

フジテレビがこのところ昼間にドラマ「踊る大捜査線」を放送していた。9月27日金曜日の夜には映画「踊る大捜査線 THE MOVIE」が放送され、今夜(30日)にはスピンオフ映画「容疑者 室井慎次」も放送された。もちろん、10月と11月に「室井慎次 破れざる者」「室井慎次 生き続ける者」が公開されるから、その盛り上げ策なのだろう。「踊る大捜査線」シリーズはドラマの映画化で成功した典型例だが、今では当たり前すぎてその当時の驚きや凄さが若い世代にはわからないと思う。コンテンツビジネスとしていかに画期的だったかを知ってもらうために、ここで整理して書いておきたい。
テレビドラマのスタッフそのままで映画を制作
まず知って欲しいのは、90年代半ばに日本映画はどん底を迎えていたことだ。日本映画製作者連盟のサイトにある「日本映画産業統計」をのぞいて欲しい。1996年に「邦画」の配給収入は過去最低の230億円になった。2000年以降、この統計では興行収入(劇場での売上高)を扱っているが、90年代までは配給収入(配給会社の売上高)を示している。興行収入は配給収入のざっくり2倍なので、配収230億円=興収460億円と見ていい。2023年の邦画の興収は1481億円だったので、3分の1しかなかった。
一方、同じ年の洋画の配収は403億円で邦画の1.8倍近い。圧倒的に日本映画は弱かった。この年の邦画のヒット作は「ゴジラVSデストロイア」(配収20億円)「Shall We ダンス?」(16億円)「ドラえもん のび太の銀河超特急」(16億円)などで、「Shall We ダンス?」は奇跡のヒットだが、ゴジラとアニメでなんとか保っていた。もちろんこの年も「岸和田少年愚連隊」「キッズ・リターン」「スワロウテイル」などのちに名作と呼ばれる日本映画は数多く公開されているのだが、興行的には箸にも棒にもといった感じだった。
私は当時、コピーライターとして映画の宣伝に関わっていたが、こんなことやってたんじゃ日本映画が産業として消えてなくなると危惧していた。本数を減らしてもっとマーケティングに予算をかけるべきと訴えたが、日々の仕事に追われる映画業界に聞く耳を持つ人はいなかった。
「踊る大捜査線」は97年1月クールのドラマで、決して視聴率がものすごく高かったわけではないが、一部に熱い支持者がいた。毎回10%台だったのが徐々に伸びていた。有名な話だが、最終回で20%に達したら映画にしてくださいと織田裕二はプロデューサーの亀山千広に頼み、本当に20%になったので約束を守って映画化が決まった。
この時、亀山は映画にするなら映画のスタッフでと考えた。実は亀山は学生時代映画青年で、ATGの作家性の強い映画を愛していた。自分たちテレビ界の人間が映画に関わるなんておこがましいと思ったのだ。
ところが、織田裕二もドラマの演出をしていた本広克行も、猛反対。テレビの作り手がそのまま映画も作るべきだと主張した。ファンたちはテレビドラマを愛しているのだ、映画とテレビにもう違いはない、と。亀山は聞き入れて、ドラマと同じく本広を軸にスタッフィングした。
だがドラマの制作会社は子会社の共同テレビ。当時の映画はフィルム上映だったので、特に納品形態がテレビとは全く違う。そこで白羽の矢が立ったのが制作会社ROBOTだった。本広はROBOTの特別契約の社員だったし、ROBOTはフジテレビの映画「ラブレター」を制作していたので最適だったようだ。
これがすべてを決めた。映画を映画の作り手ではなく、テレビの作り手がそのまま制作する。当時は実験的なやり方だったが、このトライアルがテレビと映画の歴史を変えた。98年10月31日、正月興行がスタートする前に「踊る大捜査線 THE MOVIE」は公開された。
実写映画の興行の常識を一変させた「踊る」シリーズ
私は当時、ROBOTとCM制作でつきあいがあり、阿部社長も可愛がってくれた。「踊る」の公開直前にROBOTで社長が私を見つけると「踊るはヒットすると思うんだよ!10億か、いや15億はいく!」とやたら興奮して言った。先述の通り、実写の映画では「Shall We ダンス?」の16億円が奇跡といわれた中で、15億円は無理があると思った。
ところが公開日に、映画館のチケット売り場に行列ができていると聞いて驚いた。私だけでなく、映画界もテレビ界も業界がみんなびっくりした。当時、チケットはネット販売なんてやってないので当日にチケット売り場で入場券を買うものだった。行列ができるなんて、洋画でも滅多にないことだった。
「踊る大捜査線 THE MOVIE」は毎週業界を驚かせ続け、興行はお正月映画も吹き飛ばすように続いて年を越した。最終的には配収50億円を達成。興収では101億円だと言われている。奇跡と言われた「Shall We ダンス?」は配収16億、興収に換算すると32億円。「踊る」がどれだけすごいかわかるだろう。
ドラマをそのまま映画にしたから成功した。それが正しかったことを示す反証がある。98年のドラマ「GTO」だ。説明不要だろうが、反町隆史主演の学園ドラマでこちらは放送時から大人気。視聴率は26%でスタートし、最終回は35%に達した。すると当然、これを映画化すれば「踊る」以上にヒットすると考えるだろう。
ところが映画版「GTO」は99年12月に公開されると興収13億円に終わった。今回はお正月映画として業界の大きな期待を背負っていたにも拘らずだ。なぜかは何とも言えないが、一つ言えるのは、ドラマ版とスタッフが全く違っていたのだ。さらなる推測も私にはあるが、それは後述する。
「踊る」に話を戻すと、映画化1作目がヒットすると2作目が作られ「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!」のタイトルで2003年7月に公開された。今度は堂々の夏休み映画だ。また業界中が驚いたことに、興行収入は173億円!実写邦画としていまだに破られてない記録だ。1作目も驚いたが、それを超えるとは本当に私も驚いた。もちろん1作目同様、テレビドラマと同じスタッフで制作はROBOT。中身も映画だからと国際的な陰謀などに無理にせず、汐留署の仲間たち、本庁の室井との信頼をベースに物語が展開された。
そしてまた驚いたのが、スピンオフだった。2005年に「公証人 真下正義」「容疑者 室井慎次」が相次いで公開され、興収42億円と38億円の大ヒットになった。前者は汐留署の後輩をユースケ・サンタマリアが、後者は本庁の室井慎次を柳葉敏郎が演じた。人気キャラクターを人気役者が演じたとは言え、本編の主人公が登場しない映画が40億円だ。「Shall We ダンス?」が奇跡と言われたのは何だったのか?
本編と併せて、この2本のスピンオフがまたヒットしたことが、テレビドラマ→映画のパワーを示していると思う。もちろんこの2本も同じスタッフだが、「容疑者 室井慎次」は監督を脚本家の君塚良一が兼務している。、
「踊る」シリーズが残したものと「室井慎次PJ」への期待と不安
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績