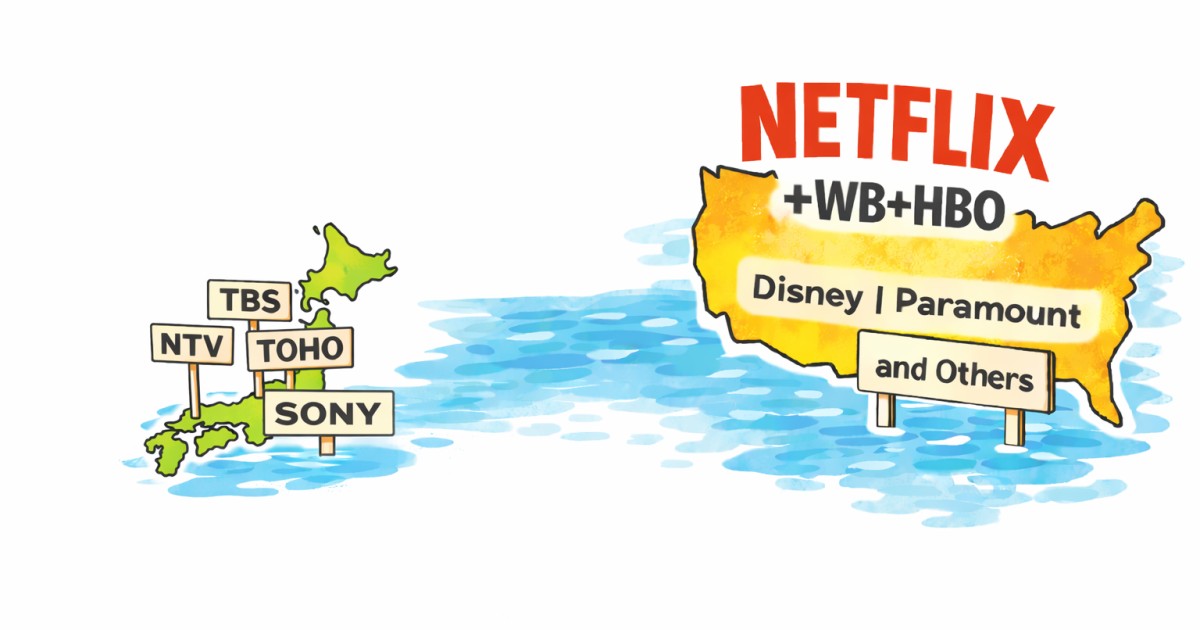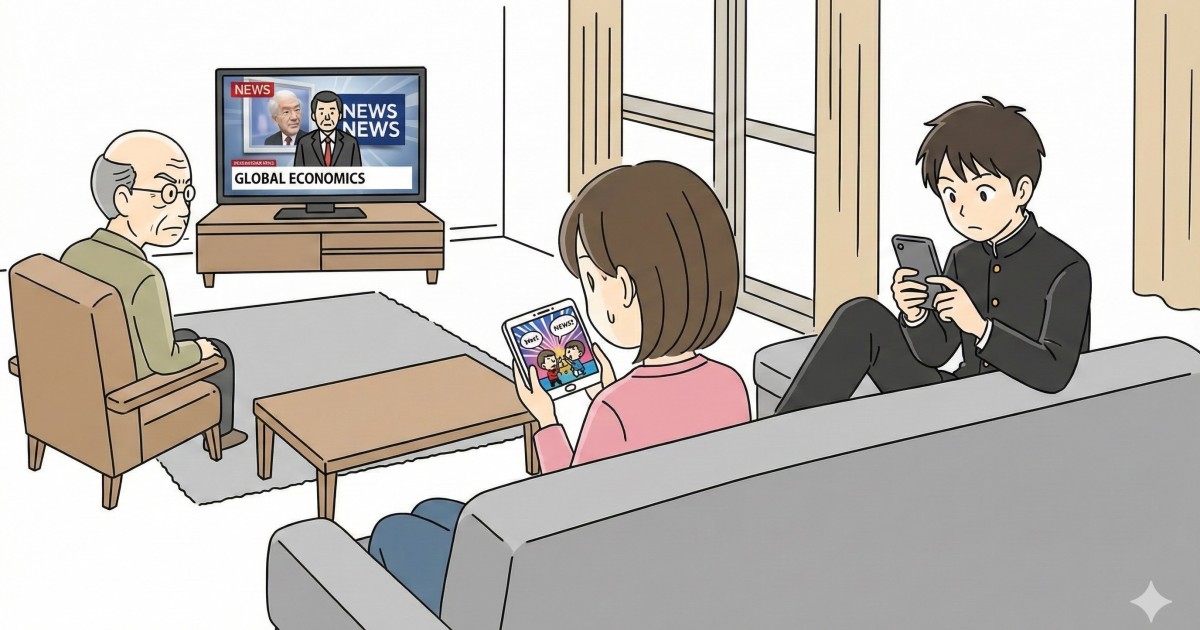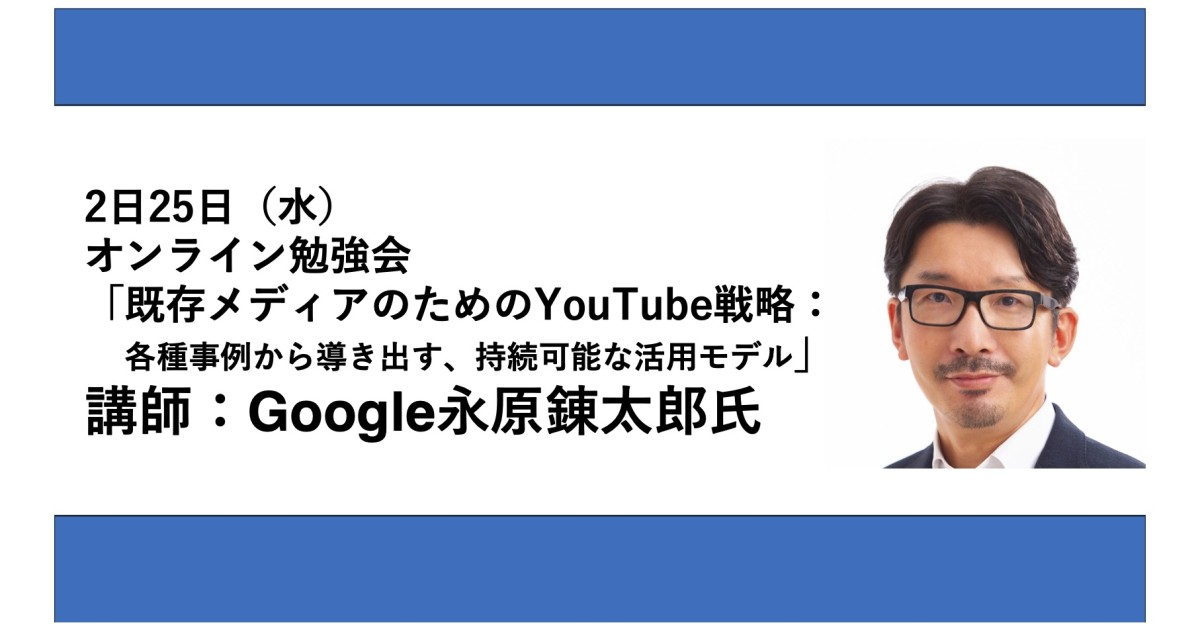映画「ブラック・ボックス・ダイアリーズ」にはブラック・ボックスがある〜暴く側が問題を暴かれる残念さ

情報を入れずに映画を見て感じたモヤモヤ
映画「ブラック・ボックス・ダイアリーズ」が品川Tジョイでの単館公開から全国に拡大した。ぜひみなさん、見てみてほしい。今から私が書くことはこの映画への批判だが、決して見るなと言いたいわけではなく、むしろ自分の目で見てあなた自身で評価してもらいたい。
私は伊藤詩織氏の性被害は本当にひどい事件だと感じていた。民事裁判で被害が認められた時は心から安堵した。
一方でそのドキュメンタリー映画が日本での公開前から一部で批判されていることはうっすら知っていた。ホテルの防犯カメラの映像の無断使用があったとか。だができるだけそうした情報は耳に入れないで映画を見た。
見ている最中、モヤっとした場面がいくつかあった。これ、ほんとにリアルなの?と感じてしまう場面があったのだ。
モヤモヤしつつエンドクレジットで、またモヤモヤがふくらんだ。「一部の音声は変えてある」「ホテルの映像は加工している」確かそんな内容の2つの文章がさらっと出てきて、ちゃんと読み終わらないうちに画面の上に消えてしまった。
ええー?!それどこのことだ?
もちろん後者は2回ほど出てきたホテルエントランスの防犯カメラ映像のことだとすぐわかる。音声を変えたのはどこだろう?特にボイスチェンジャーをかけたような声はなかったはずだが。
こういうクレジットは当該シーンで入れないと何が何だかわからない。防犯カメラ映像も、使われている場面で加工について表示しないとあとからでは確認しようがない。大事なことをはぐらかしているようで、観客に対して誠実ではないと感じた。
どこの音声を変えているのかも含めて、私はこの映画について猛然と情報を探った。多くの記事が出ていて賛否両論それぞれを読んだ。その結果、モヤモヤはガッカリに変わってしまった。伊藤詩織氏を信じられなくなっている。
ドキュメンタリーとしてより、人間としての問題
すでにあちこちの記事で、この映画の法的問題や、ドキュメンタリーの作り方の問題が書かれている。映画を見た人はぜひそうした記事を読むといいと思う。
ここではもっとシンプルな問題に絞って書く。伊藤詩織氏の捜査員Aへの仕打ちについてだ。先述の「音声を変えた」とクレジットにあるのは、映画に出てくる捜査員Aの声らしい。伊藤氏のWEBサイトに断り書きがあった。
オリジナル版のものから一貫して、顔など特定できる映像は使っておらず、音声は声質加工を施したうえで使用しています。日本版では音声をさらに加工して編集しています。
この捜査員Aは伊藤氏の性被害について当初担当した警視庁の人物だ。最初は多くを語らなかったが、徐々に心を開いてくれた。「逮捕しに成田に行ったが寸前で逮捕できなかった」という重要な情報もくれた。伊藤氏が「ブラック・ボックス・ダイアリーズ」の書籍化を報告すると、喜んでくれた。ただ、彼の声はあらかじめ断りなく録音したものを使用していたらしい。これについて、「公益通報者」かどうか、情報源秘匿に反するかどうかが議論の一つになっている。そうした専門的な言い方の前に私が思ったのは、伊藤さんが捜査員Aに対して、人間としてやってはいけないことをした、ということだ。
伊藤さんは捜査員Aを裏切った
この捜査員Aは、逮捕できなかったことが彼も悔しかったのか、途中からはっきり伊藤氏にできる限り情報を伝えようとしていた。だからこそ、成田での話も伝えたのだろう。一度は直接会っている。なぜか、途中で担当を外されているのは、彼が組織に刃向かったからかもしれない。
そんな彼とのやりとりを伊藤氏はこっそり録音していて、映画の中で使った。これは裏切りと言っていい、ひどい仕打ちだと思う。ドキュメンタリー作家としての前に、人間として。
それでも伊藤氏が、逮捕を実行しなかった捜査員Aをどうしても許せないなら、本人の許諾をぶっちぎるのもありだとも思う。だが彼女は、そんな覚悟でAの許諾を取らなかったか、はっきりしない。伊藤氏は音声を変えたから、「外部の人は(捜査員Aが誰かを)特定できない」と説明している。彼の立場を守ろうとしたと受け取れる。だが、警察内部の人々には捜査員Aが誰かわかるに決まっている。全然守れていない。
それでいて、会見でこの点を聞かれると・・・
「(性暴力)サバイバーとしての権利だ。なぜ逮捕が阻止されたのか、知る権利がある」と語った。
自分は被害者として権利があり捜査員の立場をケアする必要などない、と言っているわけだ。だったらAの音声を変える必要もないのでは?
映画の最後に「捜査員Aは今も警視庁にいる」という文字が出てくる。だから彼を守れたという意味か?伊藤氏のAへの態度はしっちゃかめっちゃかだ。捜査員Aは自分の音声が知らない間に録音されていて、映画で使われていると知った時、どう思っただろう。私なら人間不信に陥るだろう。
また、警視庁内での彼の立場はどうなったか。クビにはならないまでも、左遷の憂き目にあったかもしれない。伊藤氏はドキュメンタリー映画を作ることで、彼を晒し者にしたも同然だ。声を変えたことは何の意味もない。何度も言うが、人間としてひどい行為だ。
性被害を証明する必要はなかったのに
伊藤氏は今後、ジャーナリストとして活動する際、警察内部の情報は得られないだろう。こっそり録音されるかもしれない取材者に、迂闊にものは言えない。
裁判で寄り添ってくれた西廣弁護士も裏切った。となると、今後は弁護士にも取材を断られるかもしれない。
いや、誰からも取材を断られるのではないか。知らない間に会話を録音されて映像で使うかもしれない人物なのだ。ジャーナリストは信頼が命なのに、取材相手に信頼されない取材者になってしまった。そんなことまでして、伊藤氏は捜査員Aの音声やホテルの映像を強引に使った。私はその理由もよくわからない。
それらによって、自分が性被害者だと証明できるということだろうが、民事とは言えすでにそれは証明されている。どうして今さら証拠映像や音声を映画で使う必要があったのか。
確かに防犯カメラの映像は”強い”。ドアマンの証言もインパクトがある。だがそれらは性被害の直接的な証拠ではない。泥酔して足取りもおぼつかない伊藤氏を山口敬之氏がホテルに連れ込んだとわかるだけで、性被害を及ぼしている場面ではないのだ。
実際の裁判でも、部屋に着いてからの山口氏の話の矛盾が決め手だったようだ。
伊藤さんの弁護団は、室内で何があったのかについて、本人尋問で山口氏に質問を重ねた。そして、行為に及ぶまでの山口氏の説明に矛盾があることを尋問で明らかにした。
裁判でも決定的証拠になっていない映像や音声にどうしてここまでこだわったのか。すでに民事で決着が着いている性被害を、なぜあらためて「証明する」ような作り方をしたのか。その結果映画として無理が生じ、様々な異論を呼び起こしている。映画興行としてはいいのだろうが、ジャーナリスト伊藤詩織としてはどうなのだろうか。
そもそも自分の被害を自分で題材にする作り方は問題が生じやすく、いい手法とは言えなかったように思う。自分の側で一方的に描くことになり、客観性に欠ける。
例えば、裁判で勝利を勝ち取った性被害者伊藤氏が、他の性被害者たちを取材してその人たちの戦いを支援し記録する方向もあったはずだ。裁判決着後に自分の被害を証明する不思議な作品にならずに済んだだろう。
私は「ブラック・ボックス・ダイアリーズ」の、自らブラック・ボックスを作ってしまうような作り方自体に大きな問題を感じる。
ドラマ「新聞記者」でも裏切り行為をしたプロデューサー
誰かがそういう方向づけを伊藤氏に指導したのではないか。実は映画を見ていちばんモヤっとしたのは、この映画がスターサンズ製作で、プロデューサーに河村光庸氏の名があったことだ。
河村氏は映画「新聞記者」を製作し、その延長線でNetflixドラマ「新聞記者」も製作した、当時のスターサンズの社長だった。2022年、ドラマ配信後に急逝している。
亡くなった方の批判をするのは忍びないが、河村氏はドラマ版「新聞記者」を製作する際、事件のモデルとなった森友事件で自殺した赤木俊夫さんの妻、赤木雅子さんにドラマの了解を得ようとして断られた。それなのに製作を強行したのだ。
映画は事実を元にしたフィクションであり、赤木雅子さんの許諾が法的に必要とは言えない。だからと言って、了解を得るべく交渉を始めておきながらそれができないと強引に作ってしまうのは製作者の態度としておかしいと私は考える。
この問題について、配信開始当時、私はYahoo!で書いている。
ドラマ「新聞記者」でのモラルを欠いた進め方と、「ブラック・ボックス・ダイアリーズ」での許諾を無視した進め方と、似てないだろうか。
興味深いことに、ドラマ「新聞記者」では冒頭、疑惑の人物を成田空港で逮捕しようとしていた捜査官たちが、上からの電話で逮捕を中止する場面が出てくる。この部分が捜査官Aの話をもとにしているのは明らかだ。伊藤さんの取材がドラマに”利用”された形だ。
河村氏は「新聞記者」シリーズで、安倍政権批判をしたかったように思える。ドラマでも、批判したいからと言ってそこまで描くのは問題だと感じた場面がいくつもあった。
私は、伊藤氏が今回しでかしてしまった強引さ、関係者の気持ちを無視する進め方は、河村氏の指示が大きいのではないかと推測している。政治色の強さも、河村氏の方向づけではないか?
そして本来、その責任は監督の伊藤氏よりも、プロデューサー河村氏が負うべきだった。ところが河村氏は亡くなってしまったため、この映画が孕む問題を伊藤氏が一身に担わざるを得ない事態になってしまったのではないだろうか。
見えてくる”リベラルコネクション”の濁り
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績